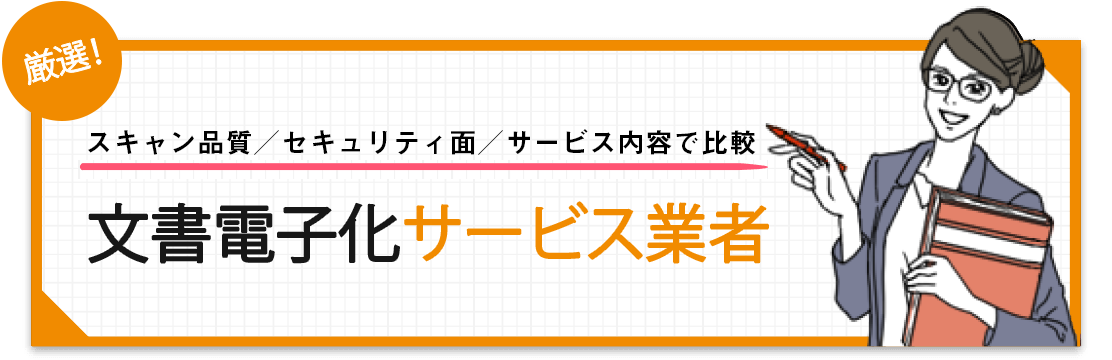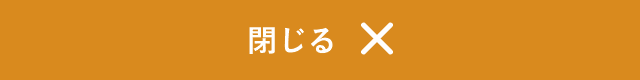公開日: |更新日:
文書/書類電子化サービス業者を10社比較
文書/書類の電子化とは
契約書やカタログ、マニュアル、帳票などを電子化(データ化)することを指します。
PCやクラウドサービスを利用して業務を進める会社が増えた昨今では、文書や書類を速やかに共有し合うことが「業務効率化」につながります。また、重要な文書や書類を紛失するリスクを防ぎ、社外から持ち出せないように対策もしやすくなるでしょう。
文書/書類の電子化の進め方
文書/書類の電子化を進める際は、取捨選択して優先順位をつけてスキャンしていくことや、解像度・形式についてルールを設けて保管場所を決めておくことが重要です。
電子化した後はファイル名を変更して整理し、検索しやすくしておくのも忘れてはいけないポイント。印刷された文字を読み取ってデータに変換する「OCR処理」も進めるのがおすすめです。
文書/書類電子化サービス業者を比較表
電子化の作業は外部の業者に委託することができます。
サイト内で掲載されている業者の品質・セキュリティ・サービス面それぞれの重要項目を比較してみました(調査日時:2021年11月)。スキャニングで業務効率化を図りたい方は、必見です。
| 会社名 | 品質 | セキュリティ | サービス | 価格 (A4 1枚あたり) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文書情報管理士 | ISO9001 | Pマーク | ISO27001 | 出張対応 | e-文書サービス | ||
| ジェイ・アイ・エム |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5円~ |
| 宏和 |
○ | - | ○ | - | ○ | - | 記載なし |
| うるるBPO |
○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 4円~ |
| 大塚商会 |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5円~ |
| アクセア |
- | - | ○ | ○ | - | - | 7.7円~ |
| シスプロデータプロ |
- | - | ○ | - | - | - | 4.7円~ |
| 川又感光社 |
- | - | - | - | - | - | 80円~ |
| 株式会社日本パープル |
○ | - | ○ | ○ | - | - | 記載なし |
| 東武デリバリー株式会社 |
- | - | ○ | ○ | - | - | 記載なし |
| パナソニック文章電子化・ 管理ソリューション |
- | - | ○ | - | - | - | 記載なし |
ジェイ・アイ・エム
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | ○ |
| e-文書サービス | ○ |
宏和
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | - | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | - | |
| サービス | 出張対応 | ○ |
| e-文書サービス | - |
うるるBPO
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | - | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | ○ |
| e-文書サービス | ○ |
大塚商会
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | ○ |
| e-文書サービス | ○ |
アクセア
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | - | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張サービス | - |
| e-文書サービス | - |
シスプロデータプロ
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | - | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | - | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | - |
川又感光社
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | - | |
| セキュリティ | Pマーク | - |
| ISO27001 | - | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | - |
株式会社日本パープル
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | - | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | - |
東武デリバリー株式会社
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | - | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | - |
パナソニック文章電子化・管理ソリューション
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | - | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | - | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | - |
文書/書類電子化サービス業者の特徴を総まとめ
上記で比較した文書電子化業者の特徴やスキャン価格などを一部紹介します。
ジェイ・アイ・エム
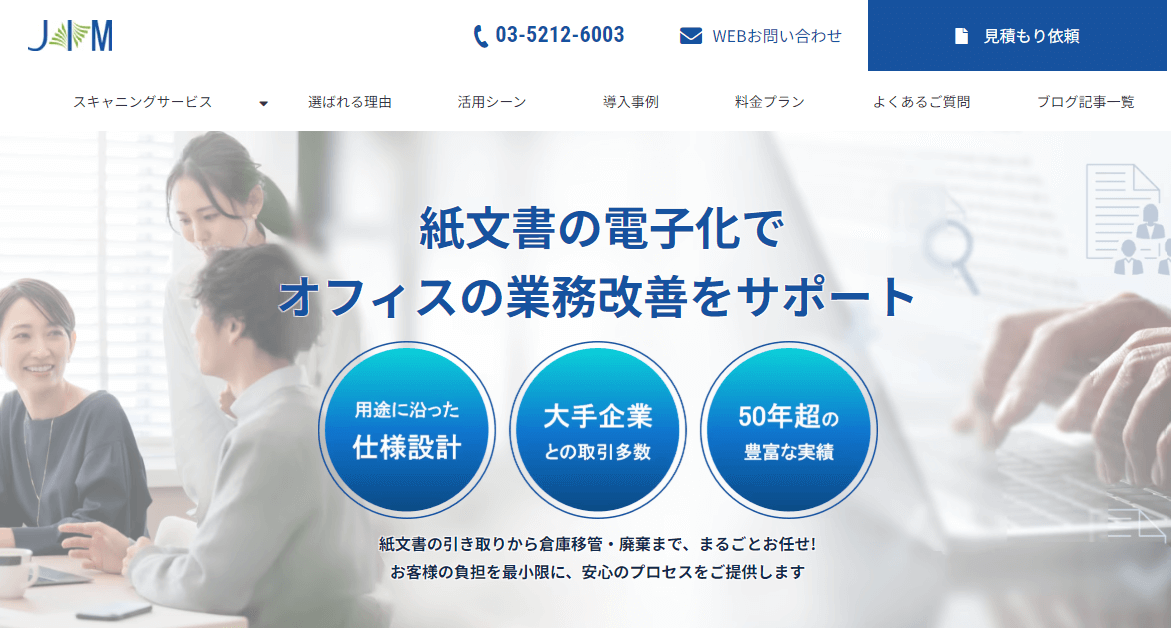
引用元:ジェイ・アイ・エム公式HP
(https://scan-jim.com/)
| スキャン品質 |
|
|---|---|
| セキュリティ面 |
|
| サービス内容 |
|
| 文書電子化の価格 |
価格はお客様のご要望に合わせて様々なプランをご用意しており、A4・1枚あたり5円(税別)~で対応可能です。図面の電子化のプランもご用意しており、A2サイズ150円~となっています。 文書電子化のサービスを利用するためには基本料(33,000円)が必要です。 100枚の文書電子化を行う場合は
また、すべてのコースで紙の状態(劣化・紙質・ファイリング状態など)による追加料金や資料の受け渡しのための別途費用が発生します。書類の状態により、価格は変化するようです。 また、文書の電子データ化だけでなく、図面の電子化も受け付けているのが魅力のひとつ。さまざまな種類の書類をまとめて電子化できるでしょう。 |
うるるBPO

引用元:うるるBPO公式HP
(https://www.uluru-bpo.jp/)
平成26年の創立ながら実績は豊富
ノウハウを駆使しBPO導入をサポート
価格:A4・1枚あたり4円~※価格は、2021年11月の情報です。
公式サイトに税の記述はありませんでした。
| スキャン品質 |
|
|---|---|
| セキュリティ面 |
|
| サービス内容 |
|
| 文書電子化の価格 |
価格はA4・1枚あたりADF(自動読取装置使用)対応で4円~・フラットベッド(手置き)15円~です。 受注承り最低価格(単価×枚数)は77,000円からとなります。100枚の文書電子化を行う場合は
ADFを使用する場合は別途、裁断費用100円/冊が必要となります。A4サイズ以外の対応、解像度、カラー対応により価格が変動します。また、お預かりする原本の状態によってはADFが使用不可と判断する可能性があるので注意が必要です。依頼数によって最大20%割引が適用となります。 ※価格は、2021年11月の情報です。 |
アクセア

引用元:アクセア公式HP
(http://www.accea.co.jp/)
| スキャン品質 |
|
|---|---|
| セキュリティ面 |
|
| サービス内容 |
|
| 文書電子化の価格 |
※価格は、2021年10月の情報です。 |
株式会社日本パープル

引用元:日本パープル公式HP
(https://www.mamoru-kun.com/
company/)
| スキャン品質 |
|
|---|---|
| セキュリティ面 |
|
| サービス内容 |
|
| 文書電子化の価格 |
|
シスプロデータプロ
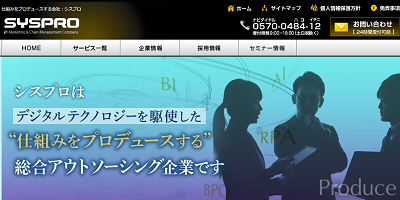
引用元:シスプロデータプロ公式HP
(http://www.syspro.co.jp/)
紙文書1枚から対応可能!
高精度・高セキュリティが強み
価格:A4・1枚あたり4.7円~
※価格は、2022年8月の情報です。
公式サイトに税の記述はありませんでした。
| スキャン品質 |
|
|---|---|
| セキュリティ面 |
|
| サービス内容 |
|
| 文書電子化の価格 |
【スキャン価格】※3万円以上依頼する場合の料金
【紙文書のデータ化・電子化】
|
宏和
| スキャン品質 |
|
|---|---|
| セキュリティ面 |
|
| サービス内容 |
|
| 文書電子化の価格 |
|
ヤマトシステム開発

引用元:ヤマトシステム開発公式HP
(https://www.nekonet.co.jp/
service/it/image_trace/image_trace)
| スキャン品質 |
|
|---|---|
| セキュリティ面 |
|
| サービス内容 |
|
| 文書電子化の価格 |
|
※2020年3月23日現在、ヤマトシステム開発では文書の電子化サービスを休止しているようです。
パナソニック文章電子化・管理ソリューション

引用元:パナソニック文章電子化・管理ソリューション公式HP
(https://www.panasonic.com/jp/business/its/document.html)
| スキャン品質 |
|
|---|---|
| セキュリティ面 |
|
| サービス内容 |
|
| 文書電子化の価格 |
公式ホームページに記載がありませんでした。詳しくはお問い合わせください。 |
川又感光社

引用元:川又感光社公式HP
(http://www.k-kawamata.co.jp/business
/print/scan-service/)
| スキャン品質 |
|
|---|---|
| セキュリティ面 |
|
| サービス内容 |
|
| 文書電子化の価格 |
|
大塚商会

引用元:大塚商会公式HP
(https://www.otsuka-shokai.co.jp/)
| スキャン品質 |
|
|---|---|
| セキュリティ面 |
|
| サービス内容 |
|
| 文書電子化の価格 |
※価格は、2021年11月の情報です。 |
東武デリバリー株式会社

引用元:東武デリバリー公式HP
(http://www.tobu-tdc.co.jp/
service/scan.html)
| スキャン品質 |
|
|---|---|
| セキュリティ面 |
|
| サービス内容 |
|
| 文書電子化の価格 |
|
文書/書類電子化業者を探す際に見るべきポイント
企業にとって大切に扱うべき書類を電子化してもらうなら、信頼できるサービス業者を選びたいですよね。評判の良い業者のなかから、依頼する前に押さえておきたいポイントをまとめました。
(1)スキャニングの品質
| 品質 | 依頼から納品まで、万が一にもミスが起こると困ります。大事なのは、書類を預けてから成果物の納品までの工程を管理するシステムがあるかどうか。それが整っていれば、品質の心配はいりません。 |
|---|---|
| 技術力 | 文書に関する電子保存の方法を理解していることを表す資格があります。それが文書情報管理士です。この資格を持った社員は技術力が高く、品質を保証してくれると見て問題ありません。 |
| 設備 | 社員がどれだけ優秀でも、実際に文書を電子化するのは機器類です。図面スキャナやブックスキャナなど、さまざまな電子化に対応できるだけの機器を取りそろえているところを選びましょう。 |
| 実績 | 大量に文書の電子化をしなければならない時、スピーディーな対応をしてくれる業者が良いですよね。とはいえ、いくら速くても質が伴っていなければ意味がありません。ひとつの指標となるのが、スキャン実績。それが高いほど信頼性が高い会社と言え、クオリティーも保証してくれるでしょう。 |
(2)セキュリティ面
| 資格の取得 | 適切に個人情報を取り扱えるところだけに付与されるプライバシーマーク(Pマーク)。そして、情報の機密性や安全性が確保されていることを示すISO27001を取得しているかどうかは良い基準になります。 |
|---|---|
| 施設管理 | 大切な文書を預けるので、トラブルを防ぐために社員の入退室管理ができていると安心です。また、警備会社と連携して監視カメラを設置しているかどうかも、あわせて確認しておきましょう。 |
| 輸送体制 | 文書のお預かりや製品の受け渡しを輸送で行なう際、一般の運送業者とは別で会社独自の専用便があると不安なく預けられます。 |
| 社員教育の徹底 | 社員1人ひとりに対して、文書の取り扱い方をきちんと教育しているかどうかもセキュリティ面で見ると非常に重要です。公式サイトに明記されているかチェックしておいてください。 |
(3)サービス内容
| 提案力 | 「業務改善を図りたい」「キャビネットスペースをなくしたい」など、文書の電子化を依頼する理由は企業によってさまざまです。企業が抱えている悩みに対して的確な対応策を提案してくれる電子化サービス業者もあります。電子化だけでなく業務全体の見直しをしたいなら、提案力(コンサルティング力)に目を向けるのもおすすめです。 |
|---|---|
| 出張スキャニングに対応 | 時には社外に持ち出せない資料の電子化をお願いすることもあるでしょう。そんな時には出張対応してくれる業者もあるので、ぜひチェックしてみてください。 |
| e-文書法に対応 | 原本保存が義務づけられている帳票といった書類を「電子化して保存して良い」と容認された法律が、e-文書法です。ただ、容認されているなかにも守るべきルールがいくつかあるため、公式サイトにe-文書法に対応できると記載されている業者にお願いしましょう。 |
| 文書管理システムの提供 | せっかく電子化するのなら、文書を管理できるシステムについても案内してくれると助かりますよね。業者によっては自社開発のシステムを提供しているところや、すでに保有している文書管理システムへの登録を代行してくれるところもあります。 |
(4)電子化の価格
| 価格相場 | 文章電子化業者の価格相場はA4サイズで白黒対応300dpiなら6円/枚前後です。サイズや解像度以外でも、原本の保管状態(劣化やファイリングなど)や紙質(質感・厚みなど)によって価格が変動しますので、見積もり段階での確認が必要です。 |
|---|---|
| 単価以外の料金 | 単価以外にも基本料金の上乗せや依頼が可能な最低価格帯など業者によって、さまざまな提示方法があります。単価だけではなくその他条件部分をしっかりと確認する必要があります。 |
※文章のスキャニングだけなら安価な業者が多いですが、ただ単にデータ化するだけなのか、カテゴリ分類や他の情報と連動して検索できるようにできるのかなど、どこまでが見積もり価格に含まれているのかを確認しましょう。内容によってはその後の業務の流れに大きくかかわってくる部分となります。
文書/書類電子化サービスを依頼する時の注意点
文書/書類電子化に関する法律を知る
文書の電子化に関する法律としては、そもそも1998年に施行された「電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)」があります。加えて、2005年4月に通称「e-文書法(電子文書法)」が施行され、電子帳簿保存法が一部改正されるとともに、それまで認められていた範囲の他にも様々な文書の電子保管が可能になりました。
なお「e-文書法」は、実際には2つの法律を合わせたものと考えられています。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
そのため、文書電子化に関する法律として、まずは「e-文書法/電子文書法」と「電子帳簿保存法」の2種類があると理解しておきましょう。
また、どのような文書でも必ず電子化できるというわけでなく、管轄する法律によって電子化できる文書やそうでない文書があることも重要です。特に、電子帳簿保存法の対象となる国税関係書類の電子保管については、あらかじめ税務署長などの承認を受けていなければなりません。
参照元:厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/topics/2005/03/tp0328-1a.html
e-文書法の要件
e-文書法では、文書の電子化にあたり以下の要件を満たす必要があります。
見読性
e-文書法では、電子データ化しても紙媒体と同じような見読性が求められます。見読性とは、パソコン画面で明瞭にデータを見られる、また、プリントアウトした際にも明瞭にデータを見られることで、可視性とも表現されます。
見読性を確保するため、スキャナなどの解像度設定を適切に行うことが大切です。
完全性
e-文書法では、作成した文書を電子化したとき、作成した文書と電子化文書が完全に同じであることを証明する義務が定められています。
文書の保存義務期間中に、改ざんや消去などを受けていないことを証明するために、誰がスキャンを実行したかを示すための「電子署名」や、いつ処理を行なったかを示す「タイムスタンプ」の技術が役立ちます。
また、データの滅失や毀損が発生しないように保存する仕組みも求められます。紙の文書をスキャンする場合、原本受領から電子データにするまでの過程やスキャン品質について、記録を残す必要があります。
タイムスタンプとは?
電子文書には複製や改ざんなどの危険性があることから、電子文書が改ざんされていない原本であることを証明する技術として誕生したのがタイムスタンプです。タイムスタンプは第三者機関のTSA(時刻認証業務認定事業者)によって発行され、固有のハッシュ値や時刻情報が付与されます。ハッシュ値を確認することで、改ざんの有無を確認できます。
令和4年1月1日より施行される「電子帳簿保存法の改正」
電子帳簿保存法(電帳法)改正の背景や目的
そもそも国税関係帳簿や関連書類は紙ベースでの保存が原則とされており、日常的な業務における業務負担や紙の書類の保管コストの軽減を目的として、一定条件を満たした場合に限り、例外的に電子帳簿保存法による電子データ保存が認められていました。
その後、法改正が重ねられて保存要件が緩和されるなど電子データ保存が行いやすくなり、現在ではスキャナ保存や電子データ保存が一般的になっています。
一方、現状でも紙ベースでの保存にこだわっている企業も少なくなく、今回の改正では将来的に一層の企業のDX化などを促進させていこうとする狙いがあります。
電子帳簿保存法(電帳法)の改正内容
2022年1月以降の改正内容は大きく以下の3つのポイントに分けられることが重要です。
- 要件緩和
- 義務化
- 罰則強化
要件緩和は、国税関係帳簿や関連書類の電子データ保存・スキャナ保存の導入に関してより簡便化されるということが主旨です。例えば従来は導入の3ヶ月前に税務署長などへの申請が必要でしたが、改正後はそれらの手続きが不要となります。また、電子帳簿の保存要件についても内容が緩和されました。
一方、義務化と罰則強化については、例えば電子データで受け取った書類(電子取引書類)は、紙ベースでなく電子データで管理しなければならないという原則が適用されます。違反した企業に対する罰則も強化されるため注意してください。
電子帳簿保存法(電帳法)の要件
電子帳簿保存法では、文書を電子化する際に「真実性」と「可視性」の2つの要件を満たすべきとされています。
真実性
電子帳簿保存法で保存する文書は、税務や財務状況を証明する書類です。そのため、電子データの削除や訂正をしたことが分かるよう、操作履歴を確認できなくてはなりません。
また、国税関係書類と帳簿の相互の関連性を確認するために、互いの関連性の確保が求められます。相互関連性を裏付けるには、システム概要書やシステム仕様書、操作説明書を備えていることが必要です。
可視性
e-文書法と同様、パソコンなどの画面上でも電子データが明瞭な状態で見られるようにしなくてはなりません。プリントアウトする際も同じで、明瞭に見られることが求められます。
また、これらは速やかに出力できるように保存することが求められており、日付や金額、勘定科目など、状況に応じてデータを速やかに検索できるようにする必要があります。
e-文書法と電子帳簿保存法の違い
e-文書法は、企業などがこれまで紙で保管していた医療や保険関係、証券や建築に関係する文書など、商法や税法などで保管が必要な文書を、電子的に保存することを許可するための法律です。
それに対し、電子帳簿保存法は、所得税法や法人税法によって管理される帳簿や契約書、請求書、領収書など、税務関連の書類が対象です。
また、e-文書法と電子帳簿保存法の大きな違いは、税務署の承認の有無にあります。電子帳簿保存法を適用するには税務署の事前の承認が必要ですが、e-文書法では電子化にあたり、事前の承認は必要ありません。
デジタル改革関連法
デジタル強靱化社会の実現を目指すためにつくられた6つの関連法です。社会全体のデジタル化が加速する一方で、現行の法体系がデジタルトランスフォーメーションの「足かせ」になってしまうケースがいくつも発生したため、急ピッチで整備が進められました。
特に2019年の新型コロナウイルス感染症の流行時には、給付金の配布に遅れが生じて社会的な問題となりました。さらにマイナンバーシステムを用いた申請手続きのトラブルも相次いだことから、社会全体の早急なデジタル整備が迫られたのです。
最近では個人情報や機密情報を狙うサイバー攻撃も増加しており、データの悪用や乱用を防ぐための仕組みづくりも重視されています。
これらの要因を背景に、デジタル改革関連法は2021年5月12日に参議院本会議で可決されました。同年9月より、一部の内容を除いて施行されています。
デジタル改革関連法は「デジタル社会形成基本法」「デジタル社会形成整備法」「デジタル庁設置法」「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」の6つの法案で構成されています。
そのうちの「デジタル社会形成整備法(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律)」では、押印や書面に関する法改正が盛り込まれています。
押印義務の廃止
デジタル改革関連法ではさまざまな行政手続きにおいて押印の義務を廃止し、書面化義務の緩和が行われました。例えば、戸籍の届出関連書類では押印義務が廃止されています。
他にも公認会計士法では財務書類、抵当証券法では抵当権の申請書、建築士法では設計図書・構造設計図書・設備設計図書、宅地建物取引業法では重要事項説明書。不動産業界や公認会計士・社会保険労務士などの一部業務において、押印義務が廃止されました。
これにより、押印を前提とした書面契約から電子署名を用いる電子契約への切り替えが可能となります。今後もさまざまなビジネスにおいて押印が必要な場面がなくなり、電子署名へと移行すると考えられます。
書面化義務の緩和
押印義務の廃止に伴い緩和されたのが、書面化義務です。内閣府関係・金融庁関係・総務省関係・法務省関係・農林水産省関係・経済産業省関係・国土交通省関係の32法律で書面化義務の見直しが行われました。
例えば不動産取引では、重要事項説明書などこれまで押印が必要だった書類の押印が廃止されたことで、書面化の必要がなくなりました。これにより押印を前提としていた書面契約は、電磁的な方法で契約できるようになります。実際、2022年5月には改正宅地建物取引業法が施行され、電子契約が全面解禁となりました。
デジタル関連法案の施行により、今後も多様な業種において電子契約サービスの導入が加速するでしょう。
原本を管理する必要がある
業務上の利便性を考えれば文書の電子化が有効である一方、万一の訴訟リスクに備えて、証拠となる原本を紙媒体で残しておいた方が良い場合もあります。
そのため文書電子化においては、原本を破棄すべき場合や保管しておくべき場合など、原本の取扱いについても適正に考えることが必要です。
スキャンの解像度を確認する
書類を電子化したとしても、スキャンの解像度が低くて書類に書かれている内容が判別できないようでは意味がありません。そのため、書類を電子化するうえでスキャンの解像度はかなり重要なポイントです。ただし、スキャンの解像度が高ければ良いというものでもなく、高く設定し過ぎると次はデータ量の問題が発生します。
電子化した書類を適切に管理するためにも、文字が読める程度の解像度に調整することが大切です。また、文字や画像を判別しやすいように、スキャンする際は原本に折れ線や浮きがないかを確認することも心がけましょう。
デバイスを確認する
電子書類のデータ形式によっては閲覧できないデバイスもあるため、どのデバイスで閲覧するのかを事前に確認しておくことも重要です。スマートフォンをはじめ、タブレットやノートパソコンなど多くのデバイスが浸透しているからこそ、どのデバイスでも閲覧できるように汎用性の高いデータ形式で保存しておくのが良いでしょう。
汎用性の高いデータ形式としては、「PDF」「TIF」「JPG」などがあげられます。PDFは文字情報、TIFやJPGは画像情報のようにデータ形式によって得意とする情報が異なるため、書類の特徴に合わせてデータ形式を使い分ける必要があります。
検索性を意識する
検索性は書類を電子化する最大の強みになるので、必要な書類をすぐに閲覧できるように検索性を向上させる工夫も必要です。検索しやすいシステムを構築するには、表記揺れに注意しましょう。表記揺れとは1つの意味を2つ以上の言葉で表現することで、「パソコン」と「PC」などが表記揺れの例としてあげられます。
書類を電子化する担当者によって表記の仕方がバラバラだと情報を検索する際の妨げになるので、タイトルの統一や表記のルールなどをあらかじめ決めておきましょう。
電子化する書類データの優先順位を決める
すべての書類を電子化するとなると膨大な費用や時間がかかってしまうため、電子化する書類データの優先順位を決めておく必要があります。優先順位が決まっていれば電子化する作業を効率化でき、より使い勝手の良いデータベースを叶えられるでしょう。
電子化した書類データの保管方法を決める
電子化した書類データを適切に管理するには、保管方法を決めておくことも重要です。ファイルの形式やファイル名、解像度、サイズなどにルールを決めておけば、検索性の向上にもつながります。ルールを決める際は、e-書類法や電子帳簿保存法などの規定を参考にすると良いでしょう。
ファイルの保管場所
ファイルの保管場所としては、社内のファイルサーバに保存してバックアップを用意する、クラウドストレージを利用して保存する、などの方法があげられます。
サイズ
ほとんどの書類のサイズはA4のため、電子化する際も原本に合わせてA4サイズに統一して保存するのがおすすめです。
ファイル形式
書類を保存する場合は、データ量の少ないPDFでの保存がおすすめです。そのほかにもJPGなどの画像ファイルとして保存する方法も考えられるため、どのファイル形式で保存するのかを事前に決めておきましょう。
格納するフォルダの構成
データを格納するフォルダの構成を事前にしっかり決めておくと、必要なデータをスムーズに見つけやすくなります。
データベース化
電子化する際に契約先や契約日などの書類の属性データも合わせて入力しておくと、電子書類のデータベース化を叶えられます。
文書/書類電子化サービスを依頼する時の流れ
(1)申込み・問い合わせ
まずは文書電子化サービス業者へ問い合わせて、対応可能な文書やサービスを確認した上で、見積りを依頼します。問合せや申込みについては、電話やメール、業者の公式ホームページの入力フォームなどを利用して行うことが可能です。業者の中には企業訪問を行って、より詳細な確認を提案してくれることもあるでしょう。
(2)概算見積もり・ヒアリング
具体的な依頼内容やスケジュール、電子化したい文書の内容・種類・量などが決まっているものであれば、どの程度の費用がかかるのか見積書の作成を依頼します。
この時、業者や文書の種類によっては現物確認を求められる場合もあるので、スムーズな見積作成のために原本を開示できるよう用意しておくことも大切です。
(3)デモンストレーション
見積で提示された費用を確認して、コスト面でのメリットを検討すると同時に、実際のデータの仕上がりやデータ形式について確認しておくことも必要です。また、文書電子化は情報管理が極めて重要なサービスでもあるため、業者の作業環境や情報管理体制などについても、具体的に信頼性を確認しておくことが望ましいでしょう。
その他、文書管理システムも同時に依頼する場合は、自社環境を想定したデモンストレーションを依頼することもポイントです。
(4)契約・納品
総合的に内容を検討して、品質と安全性やコストメリットについて納得できれば契約を行い、納品を待ちます。なお、原本に対する取扱いに関しては、契約前にしっかりと確認しておくことをおすすめします。
文書/書類電子化を依頼した後の流れ
(1)文書の回収・運搬
文書電子化を行う対象の書類や資料について、委託業者へ送付しなければなりません。なお、業者によっては製本された書類やステープラなどで綴じられた原稿に対する扱いが異なるため、事前に確認しておきましょう。また、資料が大量にある場合は、配達指定業者を案内してくれることもあります。
(2)文書/書類のデータ化
事前に依頼している仕様や契約に従って、提出した文書のデータ化が行われます。また、データ化された文書についてはCDやDVDといった媒体へ保存してもらうことも可能です。なお、どうしても持ち出し困難な重要種類の場合、業者によっては訪問して現地スキャニングを行ってくれることもあります。ただし、現地スキャニングは対応できる範囲に限界があるため、詳細の確認が不可欠です。
(3)原本の保管
電子化作業が完了した後も、万が一のリスクを想定して、原本を保管しておくことが望ましいでしょう。どの原本を保管し、また廃棄するかは、必ず事前に検討しておくことが欠かせません。なお、文書によっては、原本でなければ訴訟などで証拠採用されないケースもあるので、法的な面からも原本の取り扱いについて考えることが大切です。
(4)原本の破棄・返却
原本の破棄が必要になった場合、文書電子化を依頼した業者へ破棄を依頼することもできます。文書の破棄については、シュレッダーのように細断するだけでなく専用の機械で溶かすといった場合もあります。一方、保管すべき原本については、情報管理を厳正に行った上で速やかに返却してもらいましょう。
文書を電子化(データ化)するメリットとは?
保管スペースを削減できる(スペースセービング)
事務所の倉庫などに紙媒体で保管している文書は、紙の束やファイルを物理的に保管するスペースが必要になります。
しかし、文書をPDFなどのデータへ変換することで、膨大な量の文書データであってもコンピューターやクラウドへ保管できるようになり、スペースを有効利用することが可能です。
また、紙へ印刷するためのインク代やペーパー代といったコストを削減できる他、保管庫として別の物件や倉庫などを借りている場合は家賃等の管理コストが削減できる点もメリットのひとつです。
すぐに文書を探せる(検索の効率化)
文書をPDFファイルとしてデータ化する際、目次やしおり、OCRを付加しておけば、パソコンやWEBブラウザ、PDFリーダーなどによって即座に必要な文書や項目を検索できます。
目的の文書をスムーズに検索し、発見・活用できるようになれば、定期的に文書の保管方法や管理状況をチェックする必要がありません。
また、日付が古い文書でも関係なく即時参照できるようになるため、今後も新しい文書がどんどんと増えていくことを考えれば非常に大きなメリットといえるでしょう。
複数のデータベースを同時に検索可能な「横断検索」という機能があります。横断検索で重要なのが「ID」「年代」「資料名」「作成者」などのメタデータです。コンテンツに付与されたメタデータを取得することで、外部サーバーのデータベースの情報にもアクセスできます。
引継ぎや社員間での情報の共有ができる(情報の継承・共有化)
紙媒体の文書を他人や別部署と共有しなければいけない場合には、必要な文書を印刷して、手渡しや郵送、あるいはFAXを送る作業が必要になります。
しかし文書をデータ化することで、メールやファイルで共有したり、またはクラウドへ保管したりして、特定の権限を持った者だけがアクセスしやすくなるため、自由度が高まります。加えて、文書の内容をコピー&ペーストですぐに複製できる他、電子証明と併用すれば承認や決済の手間を省略できることも重要です。
バックアップを取ることができる
文書の電子化は、はじめこそ、スキャニングしてデータ化する必要がありますが、一度でもデータ化された文書は、それ以降のバックアップや複製が簡単になります。そのため、リスク管理として複数のバックアップを作成し、保管場所を変えておくことで、災害時やトラブル時に備えた情報の保護を行うことが可能です。
また、保存する場所をオンラインストレージなどに指定すれば、インターネットへ接続できる環境があればリアルタイムでデータを確認できるため、外回り営業や出張時などにわざわざ文書を持って運ぶ必要もありません。
セキュリティが強化できる
電子化した文書は、限られた人しか閲覧できないようにすることが可能です。パスワード設定やアクセス制限を設けて、セキュリティを強化することができます。
機密文書の場合は、コピーや印刷、メールへの添付などの持ち出し操作に制限をかけて、内部からの情報漏洩を防ぐこともできます。
管理・保管コストが大幅ダウン
紙の文書を管理するのにかかるコストは、大きく「備品代」「人件費」「保管料」の3つに分けられます。
- 備品代…紙を収納するには、キャビネットやバインダー類を購入する必要があり、書類が増え続けることに伴ってそれらの備品を買い足し続けることになります。
- 人件費…必要な文書を複数のバインダーの中から探すのには相応の時間が必要であり、それは人件費として考えるべきでしょう。また、文書のコピーにもコピー代と用紙代、さらに人件費がかかりますし、紙の文書を郵送やFAXする際にも輸送コストもしくは通信量および人件費が発生します。
- 保管料…一般的なキャビネットは1本あたり約0.25坪の占有面積が必要であり、複数のキャビネットを持つことはオフィスのスペース=賃料を圧迫することにもつながります。また、オフィス内ではなく書類を段ボールなどにまとめて外部倉庫で長期間保管するケースも考えられますので、その際は毎月の保管コストが発生することになります。
文書を電子化することで、これらのコストの大幅な削減が期待できます。
リモートワークとの相性が◎
昨今、多くの企業がリモートワークを導入していますが、稟議や決済において紙の書類を用いる場合、印鑑をもらうだけのために出社を余儀なくされるといった問題があります。
電子署名を導入することでこういった非効率な業務を解消できることから、文書の電子化はリモートワークとの相性が特によいといえます。
必要な文書を電子化することで、在宅しながら書類確認を行えるようになります。たとえばテレワークの導入に併せて文書電子化も進めた企業では、電子化によってリモートワークでも出社時と同様の業務ができるように。
その結果、女性社員が働きやすい環境が整い「時短勤務からフルタイム勤務に無理なく切り替えられた」「育児中や介護中でも勤務を続けられるようになった」という成功事例が多数あります。
利用状況を把握しやすい
文書を電子化すれば、ウェブアクセス状況や通信履歴などのログをとることが可能です。管理者は、デジタルアーカイブがどのように利用されているか詳細に状況を把握することができるでしょう。
また、これらのデータを活用して「閲覧数ランキング」や「ダウンロード数ランキング」なども作成できます。利用状況を正確に把握できれば、利用者のニーズを適切に読み取れてデジタルコンテンツの充実化を効率的に図ることが可能です。
スマートデバイスに対応できる
スマートデバイス対応機能を備えたシステムもあります。近年、スマートフォンの普及率はパソコンの普及率を上回っていると言われています。そのため、電子文書の閲覧もパソコンだけでなく、タブレットやスマートフォンを用いる機会が今後も増加してくるでしょう。
スマートデバイスは、ディスプレイのサイズや解像度がパソコンとは異なります。また、タップやスワイプなどパソコンにはない操作があるため、スマートデバイスに対応した専用のユーザーインターフェースが必要です。
多言語対応
システムの中には多言語対応機能が備わっているものがあります。デジタルアーカイブはインターネットを通じて全世界に公開されるため、コンテンツの活用を促進するためには多言語対応が必要です。利用者が日本語以外にも、英語や中国語、フランス語など表示言語を切り替えられることで、世界中の人々がストレスを感じることなく閲覧できるでしょう。
また、多言語対応されていれば分野を横断した統合ポータルの構築や、海外のポータルサイトとの連携なども可能です。さまざまな機能を使用できるようになり、可能性が広がります。
APIで他サービスとも連携できる
デジタルアーカイブを積極的に活用してもらうためには、なるべく利用者に扱いやすい検索システムであることが大切です。汎用性のない独自のシステムでは、利用者にとって使い勝手の悪いシステムになってしまうかもしれません。
APIとは、システムやアプリケーションソフトなどが他のシステムやアプリケーションソフトに対し、機能の一部を利用できるよう提供するインターフェースのこと。APIによって、他のサービスとも連携できるようになります。
BCP対策の文書/書類電子化で得られるメリット
地震大国である日本において、災害が発生した際もスムーズに事業を進められる方法を確立するのは非常に重要です。そこでキーワードとなるのが「BCP対策」。いざという時でも円滑に事業の継続や復旧作業ができるよう、具体的な対策の考え方をマスターしておきましょう。
また、BCP対策のために文書の電子化を行えば、さまざまなメリットを得られます。作業の効率化やコストの削減を狙いたい企業は、ぜひ内容をチェックしてみてください。
RPAやAI-OCRとの連携
文書や書類の電子化は単に紙媒体でなくなるだけではなく、情報共有ならびに検索性の向上などさまざまなメリットを得られます。また、RPAやAI-OCRなどのシステムを組み合わせることで、飛躍的な業務オペレーションの改善が見込めるでしょう。
RPAとAI-OCRはどちらも特徴があり、導入によるメリット・デメリットも異なります。とはいえ、どちらも連携して損はないので、それぞれの魅力をしっかりと確認したうえで導入するかどうかを検討してみると良いでしょう。
電子化のデメリット
文書や書類の電子化にはコスト削減やセキュリティリスクの低減、経年劣化の防止など複数のメリットがあります。利便性の向上というだけで導入する価値はあるのですが、デジタル化にも視認性の低下やメモを直接書き込めないなど、いくつかのデメリットが存在するのです。
ただし、メリットしかないシステムやサービスは存在しません。電子化も同じなので、ペーパーレス化実現のために電子化のメリットともにデメリットや実現のポイントを押さえておきましょう。
文書/書類電子化できる資料とは?
電子化(データ化)を行なえる書類や資料には、次のようなものがあげられます。
| 契約書 | 電子化可能な契約書は、売買契約書やリース契約書、秘密保持契約書、取引基本契約書、業務委託契約書など。契約書には法律で保存が義務付けられているものもあるため、電子化することで保管場所が不要になるメリットがあります。また、契約自体を電子化することもでき、素早く契約を交わす必要のある秘密保持契約書などは電子化向きの書類です。 |
|---|---|
| カタログ・パンフレット | カタログ・パンフレットは、電子化することで郵送費や印刷費の削減を実現できます。特に情報量の多い大学案内のパンフレットや商品カタログなどは、持ち運びや保管場所の確保が大変なため、電子化に最適です。そのほかにも、新商品の追加や価格変更などがあった際に改訂しやすいというメリットもあります。 |
| マニュアル・図面 | 新人研修で使うマニュアルや建築業界で作成する図面なども、電子化できます。たとえばマニュアルを電子化した場合、検索機能を使えば必要な情報をすぐに探すことが可能。また、膨大な量になりやすい図面は紙だと管理するのが大変ですが、電子化することで管理が楽になり、必要な図面をすぐに取り出すことができるようになります。 |
| 手書き帳票 | 手書きの申込書や報告書、注文書などの帳票も電子化の対象です。電子化によって保管場所に使っていたスぺースを別のことに有効活用できるほか、ファイリング作業の手間を省くことが可能に。また、帳票の閲覧にアクセス権限を設定することで、セキュリティ向上の効果を期待できます。 |
| 裁判書類 | クライアントからの資料をはじめ、調査資料や訴訟関連書類、判決書類、裁判記録などが電子化の対象になります。電子化した大量の原本書類はセキュリティ水準の高い外部倉庫に保管しておけば、事務所内のスペースを圧迫しません。また、電子化しておくことで膨大な資料の管理や検索がスムーズになります。 |
| 通関書類 | 通関業者や輸出入代行業者が取り扱う通関書類や申告控え、許可証、インボイス、B/L、Packing Listなどの各種書類も電子化可能です。電子化によって膨大な書類の中から目的の書類を見つけ出しやすくなり、業務の効率化を実現できます。 |
| 総務経理 | 総務や経理業務で取り扱う事業報告や監査報告、領収書、請求書などの多くは、法律で保存期間が定められています。紙で保管するとなると場所を取ってしまい、書類の分類やファイリングにも手間と時間がかかってしまうのが難点。電子化すれば保管スペースを確保する必要がなくなり、パソコンからいつでも確認できるようになります。 |
| 人事労務 | 人事労務で取り扱う雇用契約書や履歴書、タイムシート、年末調整書類などは従業員の個人情報が記載されているため、情報を漏えいしないように取り扱いには注意が必要です。電子化によって膨大な量の書類を管理しやすくなるほか、閲覧制限をかけることで情報漏えいのリスクを軽減できます。 |
| 顧客情報 | 申込書や契約書、診断書、アンケートなど顧客情報が記載された書類も電子化可能です。特に契約書や診断書は機密情報となるため、情報漏えいすると企業の信用損失につながるほか、訴訟問題にまで発展しかねません。そのため、電子化で閲覧制限をかけることで、セキュリティの向上を図れます。 |
| 製造開発 | 製造開発を行なう部署や部門では、設計図や建築図面などの書類を取り扱います。膨大な量の設計図や図面を紙で保存するとなると場所を取ってしまい、さらに紙が劣化・変色して読み取れなくなってしまうことも。電子化しておけば、保管場所や劣化・変色の問題で悩む必要がなくなります。 |
| 鋼材検査証明書(ミルシート) | 鋼材を取り扱っている工場や製作所で保管されている鋼材検査証明書(ミルシート)や切断証明書、納品書なども電子化が可能です。膨大な数になる鋼材検査証明書を電子化することで、検索や閲覧、共有を楽に行えるようになり、文書管理の効率化を実現。さらに保管スペースの削減も叶えられます。 |
文書/書類電子化できない資料とは?
特定商取引法によって書面化が求められている書類
特定商取引法によって書面化が求められている書類は、電子化できません。具体的には、契約締結時に交付すべき書面(契約書・重要事項説明書)やクーリングオフ書面などがあります。
公正証書が要求される書類
公正証書が要求される書類は電子化できません。公正証書は、公証人の前で書面作成される必要があるからです。任意後見契約書も該当します。
2022年から宅建業法と借地借家契約書は電子化が可能
宅建業法や借地借家法によって書面化が求められている書類は今まで電子化できませんでしたが、2022年5月をもって電子化が可能となりました。
電子化が可能になった書類リスト
- 媒介契約書
- 重要事項説明書
- 売買契約書
- 交換契約書
- 賃貸契約書
- 定期借地契約書
- 定期建物賃貸借契約書
- 定期建物賃貸借の説明書面
いずれ電子化される可能性がある
電子化できない理由は主に「法律上で書面での作成が求められているもの」「電子化が適切でないもの」の2つです。しかし電子化という時代の流れに合わせて、電子化を認める法律の制定や書面での作成を求める法律の改定が行われています。
現在書面での作成が必要な書類は、今すぐに電子化されるのは難しいものの、今後ほかの書類のように電子化される可能性もあります。対象の書類を扱っている方は、こまめに情報収集しておくようにしましょう。
自社内で書類を電子化(データ化)できる?
電子データ保存を導入するに当たって、自社内で各種書類の電子化を実行することは可能なのでしょうか。実の所、作業の時間や手間、コストがかかるものの文書電子化を内製化する方法はいくつかあります。
紙の書類をPDFに電子化する方法
紙の書類の場合
請求書や発注書・納品書などの紙の書類は、スキャンすることでPDF化が可能です。スキャナーまたはスキャン可能な複合機によって手順に細かな違いはありますが、基本的なPDF化の手順は以下の通りになります。
- 1.スキャナー(スキャン可能な複合機)にPDF化したい書類をセットする
- 2.メニューから「スキャン」を選択する
- 3.保存形式や保存先を指定し、スタートボタンを押す
コピー機や複合機でPDF化した場合、データをそのままFAXで送ることも可能です。オンラインでのやり取りが主流となった今でもFAXでのやり取りを希望する企業は多いため、FAXを扱う機会が多いという場合はコピー機や複合機でのPDF化をおすすめします。
ExcelやWordなどのデータがある場合
ExcelやWord、PowerPointなどで作成した文書データがある場合も、PDF形式で出力できます。手順も簡単で、文書データを開いたらメニューの「ファイル」から「エクスポート」を選択して、「PDF/XPSの作成」をクリックするだけです。
一般的には100MB以下の書類であれば、PDF化できます。ただし、ExcelやWordなどのデータで作成したPDFファイルは、データ容量が大きくなりがちなので注意しましょう。メールに添付する際に容量超過になることもあれば、閲覧時にパソコン本体に負荷がかかる可能性もあります。
そのため、ExcelやWordなどで作成したデータをPDF化する場合は、PDF圧縮で容量を小さくするなどの工夫が必要です。
ページ数が膨大なファイルや使用しているフォント・グラフィックの種類によっては、PDF化できない場合もあります。そのほか、パスワードが設定されているデータや編集制限のあるデータもPDF化できない場合があるので注意しましょう。
スマホを使ってPDF化する場合
スマホのカメラ機能を使って紙の書類を撮影し、そのデータをPDF化することができます。iPhoneの場合は、メールやメモ機能を使って電子化することも可能です。
【iPhoneのメール機能でPDF化する方法】
メール本文を入力する部分をタップすると四隅に枠のある書類マークが出てくるため、まずはそれをタップしましょう。カメラアプリが立ち上がるので、紙の書類をファインダーに合わせれば自動的にスキャンされます。完了・保存するとPDF化したファイルがメールに添付されるため、自分のパソコンや取引先にそのまま送信することが可能です。
【iPhoneのメモ機能でPDF化する方法】
iPhoneのメモ機能を開いて新規メモを追加し、キーボード上にあるカメラマークから「書類をスキャン」を選択します。カメラアプリが立ち上がるので紙書類を撮影し、保存すればPDF化は完了です。保存したファイルをトリミングすることもできます。
上記はiPhoneでのPDF化の方法ですが、Androidを使って紙の書類をPDF化したい場合は、以下の手順になります。
【Androidで紙の書類をPDF化する方法】
- 1.Googleドライブを起動して「+」をタップする
- 2.スキャンと書かれたカメラマークを選んで、紙の書類を撮影・保存する
オンラインツールを使用する場合
フリーのオンラインツールのなかには、PDF化に対応しているものもあります。ただ、文字化けしてしまうものもあるので、PDF変換のクオリティを精査したうえで利用するようにしましょう。
まとめ:書類(文書)の電子化は委託と内製どちらがおすすめ?
電子化する書類の枚数や種類が少なければ、自社内の日常業務の一環として文書の電子化を内製化することも可能です。しかし書類の枚数が膨大であったり速やかに作業を完了したかったりする場合、専門業者へ依頼することが効率的でしょう。
書類電子化の最新トレンド・統計データ
2023年度の国内ソリューションサービス市場は8兆3,732億円(前年比+5.4%)と過去最高を更新し、そのうちDX系の「デジタルソリューションサービス」が1.0兆円(同+20.4%)へ急伸しました。業界別では「製造23.4%」「金融23.2 %」「官公需21.1%」の順で投資が拡大しています。
中小企業でもペーパーレス化が加速しており、『2024年版中小企業白書』によれば 「紙書類の電子化・ペーパレス化」に取り組む企業は 2019 年比で約3倍へ増加。特にDX取組段階が“業務効率化”フェーズ(段階3)に到達した企業が26.9%まで伸びています。
参照元:一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)「ソリューションサービス市場規模調査(2022–2023年度)」(2024-09-04報道資料)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jeita.or.jp/japanese/topics/2024/0904.pdf
参照元:中小企業庁「2024年版 中小企業白書」第1部 第4章 第7節 DX(デジタル・トランスフォーメーション)
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/chusho/b1_4_7.html
安心して任せられそうなのはどこ?
書類/文書の電子化サービス業者11選
文書/書類電子化サービス業者11社ををそれぞれ比較しました。
11社のスキャニングの品質管理体制・セキュリティ・サービス内容を紹介します。
| 会社名 | 品質 | セキュリティ | サービス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文書情報管理士 | ISO9001 | Pマーク | ISO27001 | 出張対応 | e-文書サービス | |
| ジェイ・アイ・エム |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 宏和 |
○ | - | ○ | - | ○ | - |
| うるるBPO |
○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大塚商会 |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクセア |
- | - | ○ | ○ | - | - |
| シスプロデータプロ |
- | - | ○ | - | - | - |
| 川又感光社 |
- | - | - | - | - | - |
| 株式会社日本パープル |
○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 東武デリバリー株式会社 |
- | - | ○ | ○ | - | - |
| ヤマトシステム開発 |
- | ○ | ○ | ○ | - | - |
| パナソニック文章電子化・ 管理ソリューション |
- | - | ○ | - | - | - |
ジェイ・アイ・エム
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | ○ |
| e-文書サービス | ○ |
大塚商会
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | ○ |
| e-文書サービス | ○ |
DNP
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | - |
日本レコードマネジメント
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | ○ |
日立ICTビジネスサービス
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張サービス | - |
| e-文書サービス | - |
SRI
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | - |
日本通信紙
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | ○ |
| e-文書サービス | ○ |
富士フイルム
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | - |
2024年4月22日時点にGoogleで「書類電子化サービス」と検索して公式HPが表示された上位20社の内、品質やセキュリティに関わる『ISO9001』『Pマーク』『ISO27001』を取得している外部委託の企業8社をピックアップ。