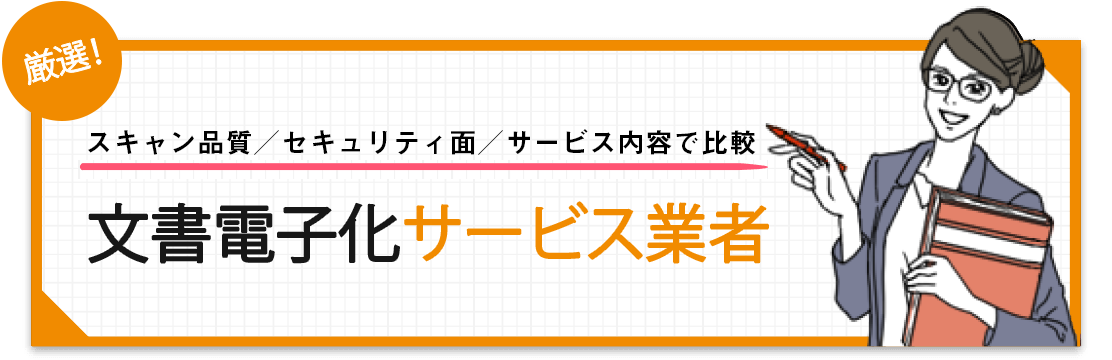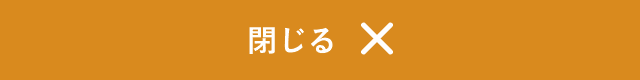公開日: |更新日:
契約書の電子化について解説
契約書の電子化とは
契約書の電子化とは、すでに取り交わし済みの紙の契約書をスキャンすることで電子データ化した上で管理や保管をすることです。
また、契約書含めて企業内で取り扱う文書は、法律により保存が義務付けられているものがいつくかあります。義務が発生する書類の電子化についての法律をe-文書法と呼びます。
これまで3万円未満のものを電子化していましたが、2015年からe-文書法が改正されて、今後は契約書や領収書は金額等を問わず電子化が可能になります。
e-文書法の規制緩和があり、今後ますます契約書は電子化しやすくなっていくと言われています。
電子契約
電子契約とは、電子証明書によって電子データに電子署名をして、書面契約と同じ証拠力が認められるものです。とは言え、データは改ざんも容易にできてしまうため、タイムスタンプなどを使って、修正が加えられていない証明を示していくことも必要になってきます。
| 紙の契約書 | 電子契約書 | |
|---|---|---|
| 書類の媒体 | 紙への印刷 | 電子データ |
| 署名方法 | 記名押印、署名 | 電子署名 |
| 日時の証明 | 日付記入、確定日付の取得 | 認定タイムスタンプの付与 |
| 送付方法 | 原本の郵送、持参 | 電子データの送信 |
| 保管方法 | キャビネット・倉庫にて原本を保管 | 自社サーバーや外部のデータセンターにて保管 |
| 書類の探し方 | 保管場所から当該契約書を探す | クラウド上で検索 |
| テレワーク対応可否 | 上司の承認印が必要な場合は出社が必須 | テレワーク対応可能 |
契約書の種類
契約書は多岐に渡ります。
業務・業態によっても、どの契約書を取り扱う比重が大きくなるのかが変わります。ここでは、いくつかの契約書の種類について確認してみましょう。
- 機密保持契約書
秘密保持契約書(NDA)や守秘義務契約書とも同義の契約書。法人間や個人間などで締結し、関連業務で知り得た秘密を第三者に開示しない契約を取り交わした証書。 - 業務委託契約書
本来は自社で行うべき業務を他社に発注する際に取り交わす契約書。委託者と受託者の間で締結し、対価として支払われる報酬に関する記載も含まれる。 - 取引基本契約書
契約当事者間で、継続的に売買や製造委託など基本的な契約条件を定めて取り交わす証書。個々の発注に関しては個別契約となり、契約書を交わさずに効率的な関係を構築するのが一般的です。 - 代理店契約書
業種によっても範囲が変わってきますが、主にメーカーの代理として営業や販売活動をしてもらうための契約内容を定めた証書。売上額によって変動のある代理店側からメーカーに支払う手数料などについても取り決めが記載されています。 - 賃貸契約書
賃貸物件を借りるための契約書。民間では住居や駐車場が主で、ビジネスシーンでは賃貸の事業所などが当てはまります。賃料や更新料などの支払い義務、借主への通知義務などの記載があります。 - リース契約書
ファイナンス・リース取引の契約条項をまとめた証書です。リース会社とユーザー間のリース契約、リース会社とリース商材の売主との売買契約が軸で、この2点の個別の契約で成り立っています。物件であれば保守契約の締結も含まれます。 - 売買契約書
売主と買主の間で、時期、対象物の詳細、数量、金額、双方の取引者などの契約内容を明記した証書です。納品場所や支払い方法なども取り決め、当事者間で確認の上で取引が行われます。 - その他の契約書
分野を限定せずに、金銭消費貸借契約書、供給契約書、工事請負契約書、ライセンス契約書、担保設定契約書、雇用契約書、保証契約書、信託契約書、受益者変更契約書、著作権契約書、譲渡契約書、広告掲載契約書、出資契約書、商品運送契約書、製造物供給契約書、合併契約書、競業避止義務契約書など、他にも取り決め毎に多様に存在します。
改めて確認しておきたいこととしては、契約をすることと、契約書を交わすことは全く別の事柄ということです。
契約書をきちんと取り交わし、契約書が存在していないという状態をつくらないことが、契約当事者の双方を守り、利することにつながります。
契約を締結したら、契約書を取り交わしましょう。
電子化できない契約書
近年、電子的手段で契約手続きできるものも増えてきましたが、電子化が適切でないと判断された書面については、法律で電子化の対象外とされています。電子化できない契約書類の一例を挙げてみましょう。
- 任意後見契約書
- 事業用定期借地契約
- 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約
- 訪問販売等で交付する書面 など
※2023年6月9日調査時点の情報です。
上記リストの中で、1~3については、公正証書による契約締結が法律で定められているため、書面での締結が必要となり電子化は認められていません。
4の特定商取引については、消費者保護のために書面を交付する義務があります。ただし特定取引に関する法律については、電子化で行うことを認める法案がすでに可決されており(※)、一定の制約が課された内容で電子化が承認される見込みとなっています。
※参照元:日本経済新聞「悪質商法規制の2法成立契約書、メールでも可能に」(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE094QL0Z00C21A6000000/)
契約書の管理・活用方法
上述のように契約書は、事業の前進に伴ってどんどんと増えていきます。
そうなると今度は文書管理が事業課題の一つとして持ち上がってくるでしょう。
書面のみの保持であれば、身近に置いておく必要があるため、スペースの圧迫や検索性の低下で、必要な時に必要な契約書を確認することが適わなくなりがちです。
オススメの文書管理は、契約書をデータ化し、原本はセキュリティ水準の高い倉庫に保管することです。
データ化した契約書はいつでも手早く契約内容を確認でき、原本が必要となる際は、倉庫からの移動の仕組みを整えておけば問題ありません。
身近なスペースを書庫として割く必要がなくなる、もしくは限りなく省略できるでしょう。
契約書の電子化において留意すべき点
ポイントは業務効率や検索性の向上、更新管理の簡素化、他の書類との紐付け確認が容易になる点です。
使いやすくならなければ意味がありません。
電子化によって、契約相手、契約種類、契約日、有効期限、更新に関する自動有無など、必要な時にすぐに対象書類を特定でき、確認すべき点をさっと把握できることが重要です。
また、契約書によっては覚書や図面などが付随していることもあるので、それらを紐付け管理できることも外せない要素です。有効期限が近い契約書について知らせるアラートが、何らかの形で通知される機能も必要でしょう。
とはいえ、電子化業務は相応の手間とコストがかかります。
かといって中途半端に実施すると、かえって非効率を招くに留まることも心配されます。
投資が無駄にならないよう、計画立てて電子化を推進しましょう。
細かな懸念点は、業者に相談してみた方がより良い結果を導き出すことができるでしょう。
電子化の際は新規発生分にも注意
文書を電子化する際、新規発生分の電子化についても注意しましょう。
というのも、過去の文書の電子化を進めているときにも新規に発生した文書は溜まっていきます。そのため、やっと過去の文書の電子化が終了したと思ったら、その間に溜まっていた新規発生分の文書が山積み…という可能性があるのです。
ただ、新規発生した文書を少量ずつ電子化すると基本料金が割高になってしまう場合も。そのため文書の量や急ぎ度とのバランスを考え、新規発生分についての文書化サイクルも検討すべきです。
契約書の電子化をするメリット
ビジネスシーンにおいて様々なメリットがあります。まず、書面のやり取りがなくなり、契約も簡単になります。契約するために持参し行き来する手間もなくなります。
そして、押印ミスや記入漏れ添付漏れなどといった書類ならではのミスも最小限に抑えられます。また、保管自体もデータとしてまとめられているため、長期にわたって保管する場合も、物理的なスペースや管理コストもかなり軽減できるのがメリットです。
コストの削減
契約書の電子化により、印紙税のコストを削減できます。紙の契約書の場合、法律により収入印紙を貼ることが義務付けられていますが、電子契約書は国税庁の見解で、印紙税法における「文書」には該当しないため、収入印紙を貼る必要がありません。
印紙税は契約種別や契約金によって異なりますが、1件につき数百円から数十万円に及ぶものもあります。1件の金額が高額でないとしても、取引先が多く契約件数が多い会社であれば課税金額も嵩むでしょう。電子化での契約は、収入印紙のコストをまるまる削減できるのが大きなメリットと言えます。
その他にも、契約書を送付する郵送料や、対面契約の場合の交通費・人件費も削減できます。
業務の効率化
紙の契約書の場合、契約書の印刷や製本、郵送手配などの事務作業が発生します。しかし電子契約ではインターネット上でやりとりを行うため、「印刷・製本」「宛名書き」「封入・投函」といった事務的作業がなくなります。
電子ファイルの整形・アップロードのみで契約書の準備と送付が完了するため、業務の効率化と生産性の向上が期待できます。
契約期限や更新の確認がしやすい
契約期間の終期は、契約内容の「見直し」「打ち切り」「継続」を検討する機会となるため、契約を交わしている双方にとって重要な時期となります。しかし膨大な量の紙媒体では、管理が大変で更新期限に気づかなかったという事態も起こりえます。
電子契約サービスでは、契約期間が満了する前のリマインド機能が備えられています。例えば「契約終了の2カ月前に自動通知」と設定することも可能。指定した時期になればアラート通知で事前に教えてくれるので、契約更新を逃しにくくなります。
コンプライアンスの強化
紙の契約書は電子契約書より信頼性が高いと思われがちですが、むしろ紙の書類のほうが改ざん防止が困難。改ざんが疑われた場合、調査に労力を要します。
しかし電子契約書の場合、文書にアクセス・閲覧したスタッフや時間がログデータとして残ります。電子署名についても、本人の署名と証明するための仕組みが備わっていたり、閲覧する人間の制限・管理ができたりなど、改ざん・不正が起こりにくいシステムとなっているため、コンプライアンス強化に役立つでしょう。
リモートワーク対応がしやすい
紙媒体での契約書の締結には、会社印の押印や印刷・製本するなど、会社へ出勤して作業する必要性があります。しかし、電子契約の場合は押印・印刷・製本の必要がなく、場所と時間を選ばずに契約を締結することが可能です。出社の必要がなく、リモートワークであっても契約業務を進められることがメリットです。
自社対応よりメリットが大きい!
文書/書類電子化業者をチェック
契約書の電子化をする際の課題
メリットも多い契約書の電子化ですが、「電子化するための手間や時間がかかる」「複合機を使用できない」「電子化したものの品質が悪くて使えない」などの課題があります。これらの問題は業者に依頼することで解決できますが、自社で電子化を行う場合は悩みの種となってしまうかもしれません。
とくに契約書は製本されているものが多く、電子化するために1ページずつめくってスキャンを繰り返します。1冊4ページ程度の製本でも1日100冊程度しか電子化できませんから、想像以上の手間と時間がかかるでしょう。複合機を独占して使用できる環境でなければさらにペースが遅れるため、「業務の合間に電子化を進めればよい」と考えるのはおすすめできません。
また、手間と時間をかけて電子化を行い、いざ内容を確認したら品質が悪くて使いものにならなかった…というケースも考えられます。契約書のとじ代部分が影になってしまっているなどのミスにも注意が必要です。
電子契約が不要なケース
導入効果があまり期待できない場合
電子契約が不要なケースとして、導入効果が期待できないケースがあります。
電子契約に切り替えるメリットとしては「印紙代の削減(コスト削減)」「事務労力・事務経費の削減(業務の効率化)」が挙げられます。
コスト削減効果が見込める会社であれば、電子契約を利用するメリットがありますが、中には判断に迷う会社もあるかもしれません。特に「契約締結数がそれほど多くない」という場合、コストに関するメリットは実感しにくいでしょう。
また電子契約へ切り替える際は、事務作業の見直しが必要になります。現在の業務体制に問題がない場合、電子化の導入を見送るのもひとつの判断と言えるでしょう。
電子契約書の併用が負担になる場合
電子契約書の切り替えは、自社だけでなく取引先との双方同意がなければ締結できません。もし取引先が紙の契約書での取引を希望している場合、従来通り紙の契約書を使用し続けることになります。
たとえ自社が電子化に踏み切った場合でも、全ての取引先の契約を一気に電子契約へ切り替えられるわけではありません。しばらくは「紙の契約書」と「電子契約書」を、取引先ごとに併用しながら運用することになります。
「電子契約書」と「紙の契約書」の併用期間中は、両契約書をどのように運用し、保管していくかの業務フローを検討する必要があります。
そのため、現状取引先の希望として紙契約書の方が多いのであれば、業務負担が長くかかることが考えられます。取引先と協議したうえで電子化を決める必要があるでしょう。
法的側面から見る契約書の電子化の課題とは
契約書の電子化は法的にも多くの側面で認められており、国もその活用を推進しています。e-文書法や電子帳簿保存法などの法律が整備され、企業活動における電子契約の普及が進んでいます。
ただし、契約相手へ書面で交付する義務がある場合や、特定の契約書については書面での締結が求められるケースがまだ多く、そのような場合には顧問弁護士や行政機関に確認し、法的要件を満たす運用を行うことが重要です。
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法は、一定の条件を満たせば契約文書を電子ファイルとして保存できることを定めています。2022年1月の改正により、事前承認制度の廃止やタイムスタンプ要件の緩和など、大幅な規制緩和が行われました。この改正により、電子化のハードルが大きく下がり、多くの企業が導入を進めています。
電子文書保存には以下の要件が求められます。
- 電磁的記録が原本と同等であることの証明(真正性の確保)。
- 保存データが改ざんされていないことを示す措置(タイムスタンプや電子署名の付与)。
- データの検索性を確保するためのフォルダ管理や索引の作成。
特に、紙の契約書から電子データへの移行に際しては、混在保存(データと紙の混在)が認められないため、完全なデジタル化が求められます。
電子署名法
電子署名法では、電子契約が紙の契約書と同等の法的効力を持つことを定めています。電子署名が正しく付与された契約データは、裁判においても有効な証拠として認められます。また、電子署名には以下の要件が求められます。
- 作成者本人であることを証明するための仕組み(電子証明書の作成・発行など)。
- 改ざんが行われていないことを保証する仕組み(認定タイムスタンプの付与)。
これにより、電子契約は高い信頼性を持ち、紙の契約書に代わる形で広く活用されています。
e-文書法
e-文書法(電子文書法)は、企業活動で必要な文書を紙ではなく電子媒体で保管することを認める法律です。この法律に基づき、企業は契約書をはじめとする多くの文書を電子化し、保存や管理が可能になりました。
電子化された文書が認められるためには、以下の条件が必要です。
- 保存データの改ざん防止措置が講じられていること。
- 保存データに関するアクセス権限や操作履歴が適切に管理されていること。
- 必要な場合に速やかにデータを閲覧・出力できること。
法的遵守のための注意点
電子契約を導入する際には、以下の点に留意してください。
- 契約相手が電子契約を承認しない場合、書面での対応が必要となる場合があります。
- 法的義務がある書面交付(例。特定商取引法に基づく契約書)には対応した運用が必要です。
- 顧問弁護士や専門家のアドバイスを受け、適法性を確認した上で導入を進めることが重要です。
契約書の電子化を進めることで、業務効率化やコスト削減を実現できますが、法的要件を確実に満たすことが、適切な運用の鍵となります。
詳しくは「e-文書法とは何か」で解説しています。合わせてご参考ください。
契約書を電子化する方法
目についた契約書を片っ端から複合機にかけて電子化を進めようとすると、計画がうやむやになるか、作業量が膨大すぎて手が回らなくなってしまう可能性があります。想定以上の工数がかかって、本来の業務がおろそかになってしまう…という状況にもなりかねません。
契約書の電子化をスムーズに進める方法は、現在の契約書の形式・保管方法を把握したうえで、契約書を用いる業務に支障が出ないような電子化計画を立てることです。
また、あらかじめ作業計画を立ててコスト算出をしておき、作業中も進捗が遅れていないか確認しながら進める必要があります。電子化は本筋の業務ではないケースが多く、工数がかかりすぎると他の業務を圧迫してしまったり、契約書の参照が必要な業務に滞りが出てしまう可能性があるためです。
自社で電子化を行なう場合
契約書の電子化を自社で進める場合は、以下のようなフローを取るとスムーズに対応できるでしょう。
- ヒアリング:契約書の量・保管方法・保管に関する要望を各部署に聞いて現状を把握する
- コスト算出:ヒアリングの結果をもとに、人員・作業日の決定・機材購入の有無などを算出する
- スキャニング:ファイル形式の統一
- 編集:ファイル名や格納場所の統一・OCR処理(画像から文字を抽出する)
- 確認:傾いたままスキャニングされていないか・番号が飛んでいないかなどの確認
- 電子化:システムへの登録
しかし、業種によっては契約書の数が多いあまり、自社で対応すると時間も手間もかかり、なかなか現実的でないというのが現状ではないでしょうか。
契約書は袋とじやホッチキス留めがされているのか、どのような分類方法を採用しているのか、どのように保管してほしいかをヒアリングしてまとめる必要があり、そもそも「忙しすぎてきちんとした分類ができていない」という状況もあるかもしれず、とても片手間でできる作業ではありません。
自社で契約書を電子化するときのポイント
自社で契約書をスムーズに行うために、以下のポイントをおさえましょう。
- 電子化を行う目的や方針を決める
まず電子化を行う目的を定め、運用イメージを考えましょう。使用頻度が高い場合は管理台帳を作成することで検索性がアップします。また、契約内容を管理したい場合は契約管理システムを導入しましょう。 - 電子化する範囲を決める
すべての契約書を電子化するには想像以上の手間や時間がかかります。そのため、どの範囲まで電子化するのかを決定しましょう。なお、台帳の作成は必要分のみに絞ることをおすすめします。 - 電子化に必要な日数や人数を割り出す
電子化する量をもとに、作業にあたる日数や人数を算出しましょう。また、いつまでにどこまで行うのかの計画を立てておくとスムーズに進められます。 - 工程ごとに作業できるよう分業する
電子化を行うためには「契約書番号の付与」「電子化」「電子化したデータの確認」といった工程があります。工程ごとに分業して作業を進めた方が効率アップにつながるでしょう。 - 検索性向上のためフォルダ構成を考慮する
電子化したデータの検索性を向上させるため、フォルダ階層やファイル名の構成を行いましょう。ただし、ファイル階層を深くしすぎるとかえって検索しにくくなる可能性もあるため注意が必要です。
文書/書類電子化サービス業者への委託でコスト削減できることも
片手間に契約書の電子化作業を外部に委託する、というのも一つの選択肢です。
契約書をばらし、分類し、複合機にかけるという「スキャニング」にかける人員コストを省くことができ、本来の業務に注力できるという利点があります。
契約書の数にもよりますが、自社で対応する人件費と外注費を見比べて判断するのが良いでしょう。
外部委託によるメリットデメリット
メリット
- 自社社員が作業を行わないため時間を有効に使える
- プロの業者がキレイにスキャニングしてくれる
デメリット
- 料金が発生するためコストがかかる
- 情報漏えいのリスクに注意する必要がある
外部委託をすることで有効に時間を使えますから、文書化作業のための無駄な人件費が発生しません。また、スキャニングは意外と難しいため、自社で行ったら不備があって使い物にならなかった…というリスクも。その点、プロの業者なら安心してお任せできます。
ただし、費用面や秘密保持の点でリスクがあるのも事実です。そのため、外部委託を行う際は料金とサービスの内容が見合っているか、また機密保守が徹底された業者であるかをしっかりとチェックしましょう。
契約書の電子化事例
事例①:事業所ごとの契約書を一括管理化できたケース
年間約4,000件の契約書が発生している燃料会社の電子化事例です。
契約書の管理は本社が行っているものの、各事業所でも契約書を保管していました。そのため、契約書の有効期限や更新の有無、有効性の把握が困難。また、解除のときに留意すべき点の確認を行うシステムも確立されていませんでした。
そこで契約書の電子化を行い、Excelベースの管理台帳を作成。従来の運用ルールをそのままに、有効期限や更新、解除の管理などの効率化を実現しました。また、契約相手のコンプライアンスチェックなども行えるようになり、管理レベルが大幅にアップしたそうです。
参照:株式会社ジェイ・アイ・エム(https://scan-jim.com/case/fuelA)
事例②:業務効率化・コスト削減を実現
業務委託契約・覚書が多数発生する企業の電子化事例です。
こちらの企業では膨大な数の業務委託契約・覚書が発生しており、その数は段ボール数箱分にもなっていたそうです。取引相手は約2,000人もおり、一人ひとりの契約書を作成するために製本・郵送・チェック・押印などに手間もかかります。紙の文書では保管スペースも必要なため、手間や時間やスペースの問題を抱えていました。
そこで文書電子化に着手し、業務委託契約書をすべて電子化。電子化によって製本や郵送の手間がなくなり、押印もスムーズに行えます。以前は2~3週間もかかっていた作業を1日で行えるほどの業務効率化を実現できました。
さらに保管スペースを確保する必要がなくなったほか、保管費や郵送費削減といった嬉しい結果も得られたのだそうです。
参照:GMOサイン(https://www.gmosign.com/media/electronic-contract/post-0011/#i-3)
事例③:電子化によって書類紛失リスクが軽減
保証会社が文書電子化を導入した事例です。
保証サービスを提供するこちらの会社では、機密書類を金庫で保管していました。しかし閲覧の度に文書を金庫から出し入れすることから、紛失や減失のリスクは避けられません。そのため電子化を検討していましたが、自社スキャニングが困難であること・外部委託をしたくても文書を持ち出せないことが悩みの種でした。
そこで出張して文書化してくれる業者と契約し、社外に持ち出せない文書は自社で文書化してもらうことを実現。社外に持ち出せる文書は業者が持ち帰って文書化したため、文書化のために業者に貸し出す自社スペースは最小限で済みました。
こうして文書の電子化を無事に終えられたことで電子データを閲覧するシステムが構築でき、機密書類を金庫から出す必要がなくなりました。
参照:株式会社ジェイ・アイ・エム(https://scan-jim.com/case/creditA)
2021年度上半期でかなり電子化が検討された背景
情報処理サービスを提供するジェイ・アイ・エムが示したデータによると、2021年度上半期では、契約書や図面、請求書などを電子化する企業が増加傾向にあったようです。
文書を電子するメリットとしては省スペース化や業務効率化、情報共有化などが挙げられますが、とくに契約書の電子化では「セキュリティレベルの向上」と「紛失防止」も大きなメリット。契約書を電子化すれば閲覧制限を設けてセキュリティレベルを向上できるうえ、紙の書類のように紛失してしまうリスクがありません。
書類や情報を管理しやすい・探しやすいというだけではなく、重要な情報を守る意味でも電子化を進めた企業が多かったのではないでしょうか。
電子化の目的で多かったのは?
ジェイ・アイ・エムによると、文書電子化を検討する企業では「省スペース化」「業務効率化」「情報共有化」を目的としていることが多かったよう。
とくに省スペース化の目的では、リモートワークが増えたことを機にオフィスの縮小が進んでおり、それに伴い書類の保管スペース削減を検討。契約書などの文書を電子化することで省スペース化を実現でき、保管にかかるコストをカットすることができます。
また、業務効率化では閲覧したい書類の検索効率を上げるため、電子化を検討。紙の書類では閲覧したい情報を探すために手間や時間がかかりますが、電子化された書類なら自席にいながら簡単に検索可能です。
さらに情報共有化では、電子化した書類を共有サーバーに保管することで、他部署の社員も閲覧しやすくなります。リモートワークが進む現在では、情報共有がスムーズになることは重要なポイントでしょう。もちろん閲覧制限をかけることもできますから、「権限を与えられた社員が自由に閲覧する」ということが叶います。
電子化を希望している方が多い部署は「経営戦略・事業開発部門・総務・経理部門」
ジェイ・アイ・エムのデータによると、とくに電子化を希望している部署は「経営戦略・事業開発部門」や「総務・経理部門」でした。契約書や図面、証憑書類などの文書を電子化したいというニーズが多かったようです。
契約書や図面などの重要な書類を電子化することで、一元管理が可能になります。社内間での情報共有もスムーズに行うことができるでしょう。また、契約書などの書類だけではなく、健康関係の書類や人事関係の書類の電子化も検討されているようです。
なお、営業・顧客支援部門などの部門でも電子化の検討が進んでいるのだそう。このことからも、さまざまな企業や部門で電子化ニーズが高まっていることがうかがえます。
参照:株式会社ジェイ・アイ・エム( https://scan-jim.com/blog/trend2021/1 )
当サイトでは、契約書のスキャニングを任せても安心な、Pマークなどのセキュリティ資格を有している文書電子化サービス業者を紹介しています。
契約書の電子化をお考えの場合は、コスト削減も見込める「委託」という選択肢もぜひご検討ください。
自社対応よりメリットが大きい!
文書/書類電子化業者をチェック
安心して任せられそうなのはどこ?
書類/文書の電子化サービス業者11選
文書/書類電子化サービス業者11社ををそれぞれ比較しました。
11社のスキャニングの品質管理体制・セキュリティ・サービス内容を紹介します。
| 会社名 | 品質 | セキュリティ | サービス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文書情報管理士 | ISO9001 | Pマーク | ISO27001 | 出張対応 | e-文書サービス | |
| ジェイ・アイ・エム |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 宏和 |
○ | - | ○ | - | ○ | - |
| うるるBPO |
○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大塚商会 |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクセア |
- | - | ○ | ○ | - | - |
| シスプロデータプロ |
- | - | ○ | - | - | - |
| 川又感光社 |
- | - | - | - | - | - |
| 株式会社日本パープル |
○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 東武デリバリー株式会社 |
- | - | ○ | ○ | - | - |
| ヤマトシステム開発 |
- | ○ | ○ | ○ | - | - |
| パナソニック文章電子化・ 管理ソリューション |
- | - | ○ | - | - | - |
ジェイ・アイ・エム
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | ○ |
| e-文書サービス | ○ |
大塚商会
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | ○ |
| e-文書サービス | ○ |
DNP
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | - |
日本レコードマネジメント
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | ○ |
日立ICTビジネスサービス
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張サービス | - |
| e-文書サービス | - |
SRI
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | - |
日本通信紙
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | ○ |
| e-文書サービス | ○ |
富士フイルム
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | - |
2024年4月22日時点にGoogleで「書類電子化サービス」と検索して公式HPが表示された上位20社の内、品質やセキュリティに関わる『ISO9001』『Pマーク』『ISO27001』を取得している外部委託の企業8社をピックアップ。
関連ページ
文書/書類電子化サービス業者を比較
サイト内で掲載されている業者を品質・セキュリティ・サービス面それぞれの重要項目を比較してみました(調査日時:2021年11月)。スキャニングで業務効率化を図りたい方は、必見です。
| 会社名 | 品質 | セキュリティ | サービス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文書情報管理士 | ISO9001 | Pマーク | ISO27001 | 出張対応 | e-文書サービス | |
| ジェイ・アイ・エム |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 宏和 |
○ | - | ○ | - | ○ | - |
| うるるBPO |
○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大塚商会 |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクセア |
- | - | ○ | ○ | - | - |
| シスプロデータプロ |
- | - | ○ | - | - | - |
| 川又感光社 |
- | - | - | - | - | - |
| 株式会社日本パープル |
○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 東武デリバリー株式会社 |
- | - | ○ | ○ | - | - |
| ヤマトシステム開発 |
- | ○ | ○ | ○ | - | - |
| パナソニック文章電子化・ 管理ソリューション |
- | - | ○ | - | - | - |
ジェイ・アイ・エム
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | ○ |
| e-文書サービス | ○ |
宏和
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | - | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | - | |
| サービス | 出張対応 | ○ |
| e-文書サービス | - |
うるるBPO
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | - | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | ○ |
| e-文書サービス | ○ |
大塚商会
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | ○ |
| e-文書サービス | ○ |
アクセア
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | - | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張サービス | - |
| e-文書サービス | - |
シスプロデータプロ
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | - | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | - | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | - |
川又感光社
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | - | |
| セキュリティ | Pマーク | - |
| ISO27001 | - | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | - |
株式会社日本パープル
| 品質 | 文書情報管理士 | ○ |
|---|---|---|
| ISO9001 | - | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | - |
東武デリバリー株式会社
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | - | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | - |
ヤマトシステム開発
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | ○ | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | ○ | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | - |
パナソニック文章電子化・管理ソリューション
| 品質 | 文書情報管理士 | - |
|---|---|---|
| ISO9001 | - | |
| セキュリティ | Pマーク | ○ |
| ISO27001 | - | |
| サービス | 出張対応 | - |
| e-文書サービス | - |